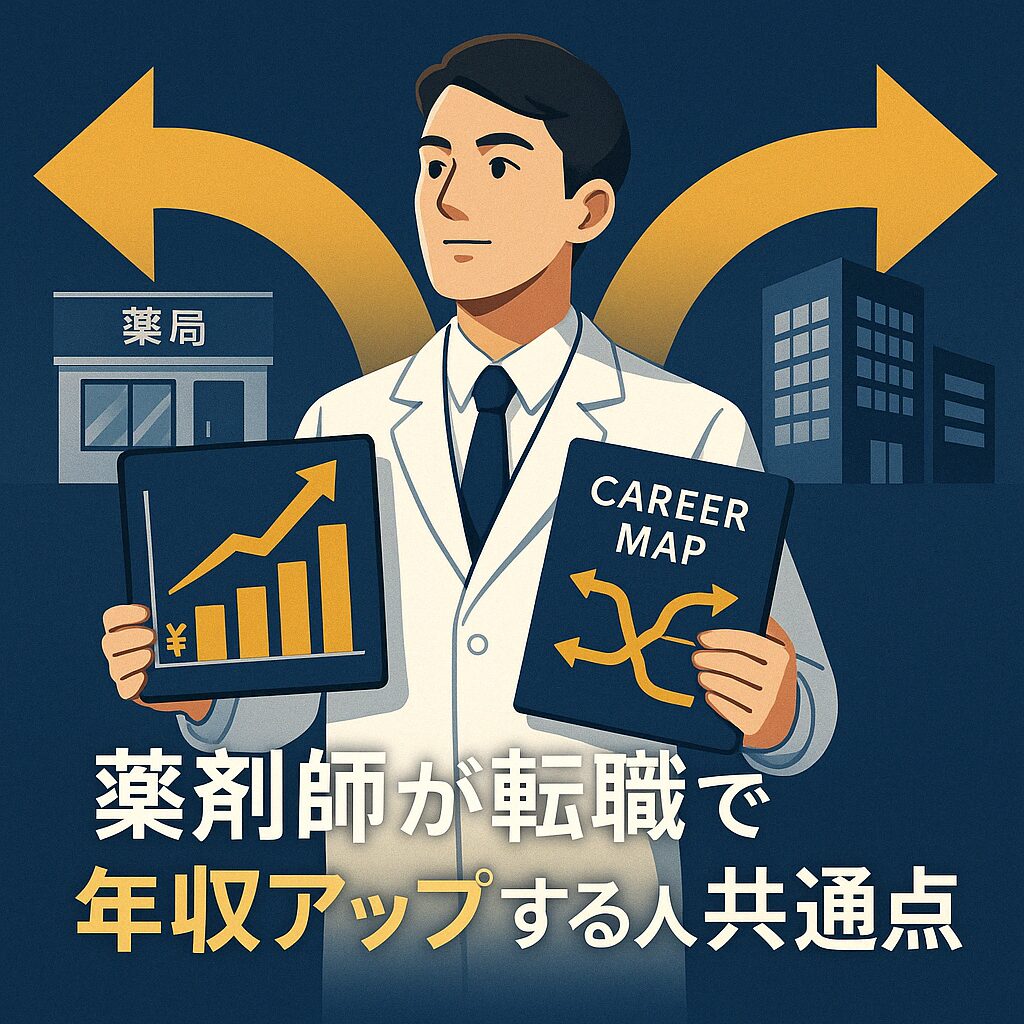病院薬剤師必携|インバウンド患者を守る英語45フレーズ&安全対策ガイド

「センセイ、Can you speak English…?」——外来カウンターで外国人患者に突然こう尋ねられ、言葉に詰まった経験はありませんか?近年の訪日外国人の急増により、病院でのインバウンド対応がますます重要になっています。英語での対応を誤れば、投薬ミスやクチコミ評価の低下に直結するリスクも。本記事では、外資系医療機器企業で8年以上働く薬剤師の視点から、①現場でよくあるトラブル5選とその回避策、②すぐ使える英語45フレーズ、③指差しツール・学習法をまとめました。英語に不安がある方でも、読み終える頃には安心して外国人患者を迎えられる準備が整う内容です。
インバウンド増加で病院薬剤師に求められる新スキル
「外国人患者と接するのは限られた場面だけ」と思っていませんか?
しかし、観光再開と航空便増加に伴い、インバウンド患者の来院数は急増しています。
特に大都市の基幹病院では、言語対応の機会が以前の2倍以上に増えたという報告もあります。
その中で、薬剤師にも求められるのは、**服薬指導や問診における“英語対応力”**と、
**文化差による誤解やトラブルを予防する“異文化コミュニケーション力”**です。
これは単なる語学スキルではなく、安全と信頼のための医療スキルでもあります。
まずは今、病院薬剤師の現場で実際に起きている変化を、データと事例から見ていきましょう。
→関連記事:『薬剤師 インバウンド 対応課題』
外来・救急で起こる言語トラブル統計
救急搬送された外国人が「薬の説明が理解できず不安だった」と感じた割合は、
ある調査では**全体の56%**にのぼります(AMDA国際医療情報センター調べ)。
また、薬歴の聞き取りミスやアレルギー確認不足による投薬ミスも報告されています。
とくに発生しやすいのは、
- 外来受付での「処方箋・症状説明」の場面
- 救急時の「既往歴・服薬状況確認」の場面
- 入退院時の「服薬指導と注意事項」の場面
つまり、薬剤師が直接英語で対応する場面が明確に増えているのです。
「翻訳アプリに頼ればいい」では済まされない局面があるからこそ、“使える英語”の準備が重要になっています。
病院ブランド・患者満足度への影響
外国人患者が日本の医療機関に期待するのは、「高度な治療」だけではありません。
わかりやすい説明・信頼できる対応・安心感あるコミュニケーションが求められます。
そしてそれが得られなかった場合、SNSやレビューサイトに不満が可視化される時代です。
ある大学病院では、英語対応研修を受けた部署の患者満足度が6ポイント向上したという報告もあり、インバウンド対応は病院全体の評価・ブランド価値にも直結しているといえます。
薬剤師が「伝える力」を持っていれば、患者だけでなく周囲のスタッフや組織にも安心が広がります。
その意味でも、“英語力×コミュニケーション”は、これからの薬剤師に必須のスキルといえるでしょう。
外国人患者対応で起こりがちな5大トラブル
「ちゃんと伝えたはずなのに…」
外国人患者とのやり取りでは、言語や文化の違いによって意図しない誤解やすれ違いが生まれがちです。
特に病院薬剤師の現場では、問診や服薬指導の説明ミスが重大な医療事故につながるリスクもあります。
以下では、現場で実際に起こったトラブルの中から、再発防止の観点で知っておくべき代表的な5例を紹介します。
「英語力が不安」「対応経験が少ない」と感じている方こそ、まずは事例を知ることが第一歩です。
→関連記事:『外国人クレーム事例集 病院版』
患者情報の聞き漏れ→重篤副作用
「薬にアレルギーはありますか?」という質問に「No」と返答した外国人患者。
しかし後に、以前に抗生物質でじんましんと呼吸困難が出たことがあったことが判明。
このような聞き漏れが、重篤な副作用を引き起こす事例が報告されています。
“Do you have any allergies?” だけでは**「食物・花粉・動物」まで含む曖昧な質問**になりがちです。
“Any allergies to medicine?” や “Have you ever had a rash or trouble breathing after taking medicine?” など、
具体的な症状や薬に絞った聞き方が重要です。
服薬時間の誤解→治療失敗
「1日3回、食後に服用してください。」——この定型文も、英語に直すと意外と誤解されがちです。
たとえば、“Take one tablet three times a day after meals.” と言っても、「起床後・昼食後・就寝前」や「朝・昼・晩とは違う時間」に解釈されることがあります。
実際に、患者が1日1回しか服用していなかったために、治療が長引いたケースも。
多くの国では「1日3回」「食後」という概念があいまいなことを前提に、“Take one tablet after breakfast, lunch, and dinner.” など、時間帯を明確に伝える工夫が必要です。
説明不足による副作用の軽視
薬剤師が副作用のリスクを説明したにもかかわらず、患者が「気にしなくていいもの」と誤認して重篤化するまで受診しなかった事例もあります。
原因の一つは、“It may cause dizziness or nausea.” といった説明が「可能性が低い=問題ない」と受け取られてしまう文化的違いにあります。
“Stop taking this and see a doctor if you feel dizzy.”(めまいが出たら服用を中止して受診)など、対応の指針を明確に伝えることで、軽視を防ぐことができます。
文化差によるクレーム・不信感
日本人には丁寧でも、外国人患者にとっては「冷たい」「説明が少ない」と感じられることもあります。
例として、「Yes/No」ではっきり答えない対応が、信頼できないと誤解されたケースがあります。
特にアメリカ・ヨーロッパ出身の患者は、明確な意思表示や情報提供を重視する傾向が強いため、
- 結論から話す
- 自信あるトーンで話す
- アイコンタクトを取る
など、非言語の対応も含めた信頼構築が必要です。
処方薬との重複・相互作用の確認ミス
観光客の中には、自国で処方された薬やサプリメントを持参している人も少なくありません。
しかし、持参薬の成分が日本の薬と重複・相互作用を起こすケースが見過ごされがちです。
たとえば、抗ヒスタミン薬の併用で強い眠気やめまいが出たという報告も。
英語での確認は、“Are you taking any other medicine, including supplements or vitamins?”
さらに “Can you show me the package?” と具体的に尋ねることで、誤用のリスクを減らすことができます。
上記5つの事例は、どれも“伝え方”と“確認の仕方”を工夫するだけで予防できるものばかりです。
次のセクションでは、こうしたトラブルを防ぐための「英語フレーズ集」と「伝え方の工夫」をご紹介します。
これだけ覚えれば乗り切れる!45フレーズ早見表
「全部は覚えきれない…」と感じていませんか?
実は現場で頻出する英語は、45個に絞れば十分対応できます。
しかも場面ごとに15個ずつ覚えるだけで、患者の安心感は大きく向上。
以下では 受付・問診/服薬指導・退院時/緊急時・家族説明 の3シーン別に、
そのまま口に出せる短いフレーズを15個ずつ掲載しました。
まずは自分の担当シーンから音読→メモ→実戦で使ってみてください。
→関連記事:『薬剤師 英語 仕事で使える基本表現』
受付・問診で使えるフレーズ15選
- Do you have an appointment?(予約はありますか?)
- Please fill in this form.(この用紙にご記入ください。)
- What brings you here today?(今日はどうされましたか?)
- Do you have a fever?(熱はありますか?)
- Any allergies to medicine?(薬にアレルギーはありますか?)
- When did it start?(いつから症状がありますか?)
- Where does it hurt?(どこが痛みますか?)
- Are you taking any medicine now?(今飲んでいる薬はありますか?)
- Do you have insurance?(保険証はお持ちですか?)
- Please wait a moment.(少々お待ちください。)
- We will call your name.(お名前をお呼びします。)
- Take a seat over there.(あちらにおかけください。)
- Can you show me your ID?(身分証を見せていただけますか?)
- Have you visited us before?(以前に来院されたことはありますか?)
- Do you need an interpreter?(通訳は必要ですか?)
服薬指導・退院時に使えるフレーズ15選
- Take one tablet after meals.(食後に1錠服用してください。)
- Take it three times a day.(1日3回服用してください。)
- Take before bedtime.(就寝前に服用してください。)
- Do not drive after taking this.(服用後は運転しないでください。)
- Swallow with water.(水で飲み込んでください。)
- Chew the tablet.(この錠剤はかんで服用してください。)
- Apply to the affected area.(患部に塗ってください。)
- Store in a cool place.(涼しい場所で保管してください。)
- Keep out of children’s reach.(子どもの手の届かない所に保管してください。)
- Finish the full course.(最後まできちんと飲み切ってください。)
- Stop if you feel rash.(発疹が出たら服用を中止してください。)
- See a doctor if pain continues.(痛みが続く場合は受診してください。)
- This may cause drowsiness.(眠気を引き起こす可能性があります。)
- Any questions so far?(ここまででご質問はありますか?)
- Please read this leaflet.(この説明書をお読みください。)
緊急時・家族説明時に使えるフレーズ15選
- This is an emergency.(これは緊急です。)
- Please stay calm.(落ち着いてください。)
- Can you breathe well?(呼吸は苦しくないですか?)
- Do you feel chest pain?(胸の痛みはありますか?)
- Are you allergic to this drug?(この薬にアレルギーはありますか?)
- We need to give you medicine now.(今すぐ薬を投与します。)
- Call me if pain gets worse.(痛みがひどくなったら呼んでください。)
- Press this button for help.(助けが必要なときはこのボタンを押してください。)
- We will take you for a scan.(検査にご案内します。)
- Your family is waiting outside.(ご家族が外でお待ちです。)
- I will explain the treatment.(治療について説明します。)
- Sign here for consent.(同意書に署名してください。)
- We are doing our best.(全力で対応しています。)
- Any questions from your family?(ご家族から質問はありますか?)
- Let us know if you need an interpreter.(通訳が必要な場合はお知らせください。)
この15個は大声・はっきり・ジェスチャーで伝えると効果的です。
今日から1日1フレーズずつでも口に出して慣れていきましょう。
45フレーズは印刷してポケットに入れるだけでも心強い武器になります。
次章では“指差しツール”と組み合わせた伝わるコツを解説します。
英語ゼロでもOK——指差しツール&アプリ活用術
外国人患者とのコミュニケーションに不安を感じる医療従事者の方へ。言葉の壁を乗り越えるための「指差しツール」や多言語対応アプリが、現場での強力なサポートとなります。これらのツールは、無料で利用でき、特別な許可も不要です。以下に、実際に利用可能な信頼性の高いツールをご紹介します。
無料PDF/アプリ3選(厚労省・AMDAほか)
1. 多言語医療問診票(厚生労働省 × 国際交流基金 × AMDA国際医療情報センター)
全23言語に対応した問診票をPDF形式で提供。内科、外科、小児科など11科目に対応しており、薬局や外来、救急の現場で活用できます。日本語との併記で、患者との意思疎通がスムーズに行えます。使用許諾不要で、無料でダウンロード可能です。
公式サイト:https://kifjp.org/medical/
2. 多言語問診票(AMDA国際医療情報センター)
英語、韓国語、中国語、フィリピン語、スペイン語、ベトナム語、ポルトガル語、タイ語に対応した問診票を提供。診察申込書や症状記入用紙など、さまざまな書式があり、医療機関での利用が推奨されています。
公式サイト:https://www.amdamedicalcenter.com/questionnaire
3. 外国人向け多言語説明資料(厚生労働省)
英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、ウクライナ語、ヒンディー語、インドネシア語、ネパール語、タガログ語、タイ語、ベトナム語の12言語に対応した説明資料を提供。診療申込書や医療費請求書など、医療機関での対応に役立つ資料が揃っています。
公式サイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokusai/setsumei-ml.html
更新頻度と信頼性チェックリスト
ツールを選ぶ際には、以下のポイントを確認しましょう:
- 更新頻度:最新の医療情報に基づいているか。
- 公式性:厚生労働省や信頼できる団体が提供しているか。
- 対応言語:必要な言語に対応しているか。
- 使用許諾:無料で使用でき、特別な許可が不要か。
これらのツールを活用することで、英語に自信がなくても、外国人患者とのコミュニケーションが円滑に行えます。現場でのトラブルを未然に防ぎ、患者満足度の向上にもつながります。ぜひ、日々の業務に取り入れてみてください。
トラブルを防ぐ7つの注意点(医療通訳士の視点)
医療現場で発生する可能性があるトラブルと注意点を医療通訳師の視点で解説していただきました。
「英語で説明したのに、なぜか納得してもらえない…」
そう感じたことがあるなら、原因は“言葉そのもの”ではなく、“伝え方”にあるかもしれません。
医療通訳の現場では、話し方・態度・文化的背景の違いが、医療トラブルや不信感につながるケースを数多く見てきました。
ここでは、医療通訳士としての現場経験に基づき、外国人患者対応時に意識すべき7つのポイントを解説します。
言語に自信がなくても、伝わる工夫さえできれば、トラブルは大きく減らせます。
話速・語調・ジェスチャー
どんなに正しい英語でも、速すぎる・小さすぎる・棒読みすぎると伝わりません。
医療通訳では、以下の3点を必ず意識しています:
- 話速:日本語の7〜8割程度のスピードで。間を取りながら1文ずつ。
- 語調:文末をしっかり下げ、指示と情報を分けて話す(命令と誤解されにくくなる)。
- ジェスチャー:指差し・表情・カードや薬を見せるなど、“視覚情報”を積極的に補う。
たとえば、“Take one tablet after meals.” を伝えるときも、
薬のパッケージを見せながら、食事を指で示し、ゆっくり話すだけで理解度は格段に上がります。
文化差を埋めるクッション言葉
同じ言葉でも、文化によって受け取り方が全く異なることがあります。
日本ではやわらかい表現が好まれますが、英語圏では「はっきり」「具体的に」伝えることが信頼につながります。
とはいえ、“You must not drive.” のような断定表現はかえって強すぎて反発を招くことも。
そこで役立つのが、**“クッション言葉”**です。
- “Just to be safe,”(念のため)
- “It’s better to…”(〜の方がよいです)
- “We usually recommend…”(通常は〜を推奨しています)
また、“Please” は便利ですが、命令に近く感じられる場面もあるため、
- “Could you…”
- “Would you mind if…”
といった依頼表現を使うことで、やさしさと明確さのバランスが取れます。
その他5つの注意点
医療通訳の立場から見て、現場での信頼構築に効果的な「+5の工夫」は以下の通りです:
- 理解をこまめに確認する
→ “Do you understand so far?” “Is this OK?” を要所で挟むと誤解を防げます。 - マスク越しでも表情を意識
→ アイコンタクト・うなずき・目元の動きが「安心感」になります。 - 「わからない」ときの逃げ道を用意する
→ “Let me double-check.” や “I’ll ask a colleague.” と言えることは安全対応の一部。 - アプリやツールは「補助」に徹する
→ 翻訳アプリはあくまで補足。主軸は「人の伝え方」に置くべきです。 - 誤解されがちな表現に敏感になる
→ “You can take this freely.” は「自由にどうぞ」ではなく、「制限なく服用して良い」と誤解される可能性あり。言い換え例:“Take as needed, but no more than 3 tablets a day.”
「通訳がいないから対応できない」のではなく、伝え方に気を配れば十分に対応可能です。
7つの注意点を意識することで、“伝えたつもり”を“伝わった確信”に変えることができます。
次章では、そうした意識を行動に変えるための“習慣化の工夫”をご紹介します。
学んだフレーズを定着させる3ステップ学習法
「覚えても、すぐに忘れてしまう…」
英語フレーズを学んでも、使う場面がなければ定着は難しいと感じる方も多いはずです。
でも大丈夫。実は、学習→使用→共有の3ステップで、記憶の定着率は大きく向上します。
ここでは、薬剤師の業務に組み込みやすいシンプルな習慣として、3つの方法を紹介します。
すべて1日10分以内でできるので、「忙しくても続けられる」学習法としておすすめです。
→関連記事:『薬剤師 英語スキルアップロードマップ』
1日3分シャドーイング
英語を「目で覚える」だけでは記憶に残りづらく、声に出すことで定着度が一気に高まります。
そこでおすすめなのが、音声を聞きながら同時に話す「シャドーイング」です。
- 英語学習アプリやYouTubeで、ネイティブ音声の医療フレーズを選ぶ
- 「1日3フレーズ」「各3回ずつ」を目安に、発音をまねる
- 毎朝や休憩時間など、“決まった時間に習慣化”するのがコツ
「発音が正確か」よりも、「口が自然に動く」ことを重視しましょう。
録音して聞き返すと、改善点も見えやすくなります。
業務内アウトプットの仕込み方
フレーズを定着させるには、実際に使ってみることが一番効果的です。
とはいえ、日常業務の中で英語を話すチャンスは限られています。
そこで有効なのが「仕込み型アウトプット」です。
- 「受付で最初に言うフレーズ」を英語で固定(例:“Do you have an appointment?”)
- 「服薬指導の1文だけは英語にする」と決めておく
- 「週に1回、外国人患者への説明を英語でリハーサルしてみる」
重要なのは、「考えなくても出てくる型」を作ること。
1つでも自然に言えるようになれば、他の表現もスムーズに口から出るようになります。
“人に教える”ことでさらに定着
フレーズを「覚える」から「使える」に変える最後のステップは、人に伝えることです。
同僚や後輩に、「このフレーズ便利だったよ」と共有することで、記憶が強化されます。
- 自作の「よく使うフレーズ一覧」を共有
- 勉強会や朝礼で“1分英語”として紹介
- LINEグループやSlackに「今週の使えるフレーズ」を投稿
教える側になることで、どこが難しいか・どう伝えたらいいかも見えてきます。
これはまさに、「学びの出口を自分で作る」最高の方法です。
この3ステップは、どれも今日からすぐ始められます。
次章では、学んだ英語力をどうキャリアアップにつなげるかを整理していきます。
まとめ
インバウンド患者の急増を受けて、病院薬剤師にも「英語対応力」が求められる時代が来ています。
この記事では、頻出トラブルの実例と45の英語フレーズ、指差しツール、学習法を紹介しました。
「英語が苦手」でも大丈夫。伝えたい気持ち+備えたフレーズがあれば、
明日からの現場で“伝わる安心”を提供することができます。
また、英語力を高めた薬剤師は、企業・外資系・教育研修の分野でも高く評価されるようになっています。
次のステップとして、あなたのスキルをどう活かすか、転職やキャリア形成の選択肢も広げてみましょう。
【「英語が不安で転職に踏み出せない…」そんな薬剤師の方へ】
TOEICの目安、英語力が活きる職種、学び直し法までを1本にまとめた実践ガイドをご用意しました。英語を“武器”にしたい方は、ぜひ参考にしてください。
薬剤師×英語完全ガイド|TOEIC・外資転職・学習法を実例で解説
【企業に興味はあるけれど、何から始めればいいか分からない方へ。】
業界・職種の全体像と転職5ステップを、実例とともにわかりやすく解説しました。まずはこちらのガイドで、あなたのキャリアの方向性を整理してみませんか?
【転職や昇給が難しいと感じたら、副業という選択肢もあります】
薬剤師に人気の副業17選と、始め方・税金対策までを実践的に解説。キャリアに新しい可能性を加えるヒントを、こちらにまとめました。
薬剤師の副業完全ガイド|+5万円を目指す実践17選と税金対策
【「やっぱり気になる薬剤師の年収。」】
年収が上がりにくい理由と、転職・昇進・副業という“年収アップの三本柱”を、薬剤師×FPの視点でやさしく解説。将来に向けて収入を見直したい方は、ぜひ参考にしてください。