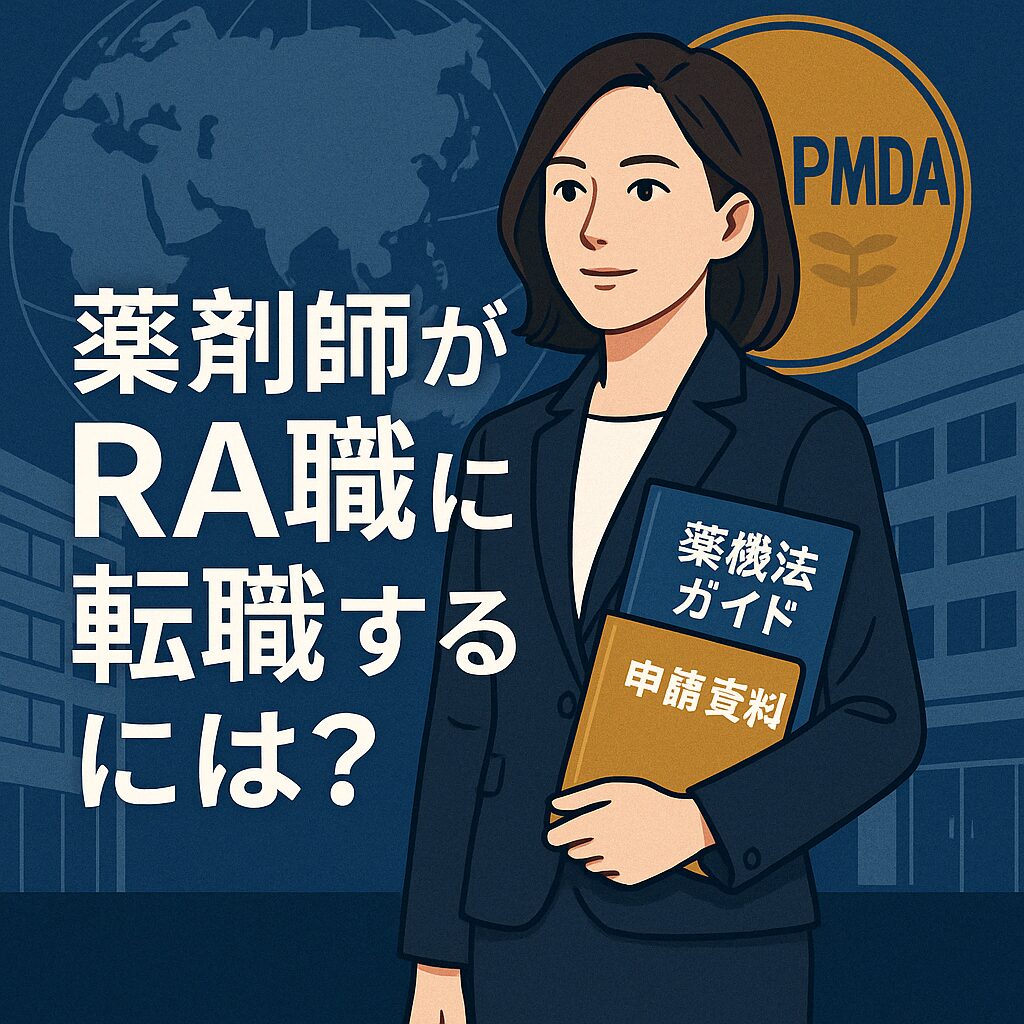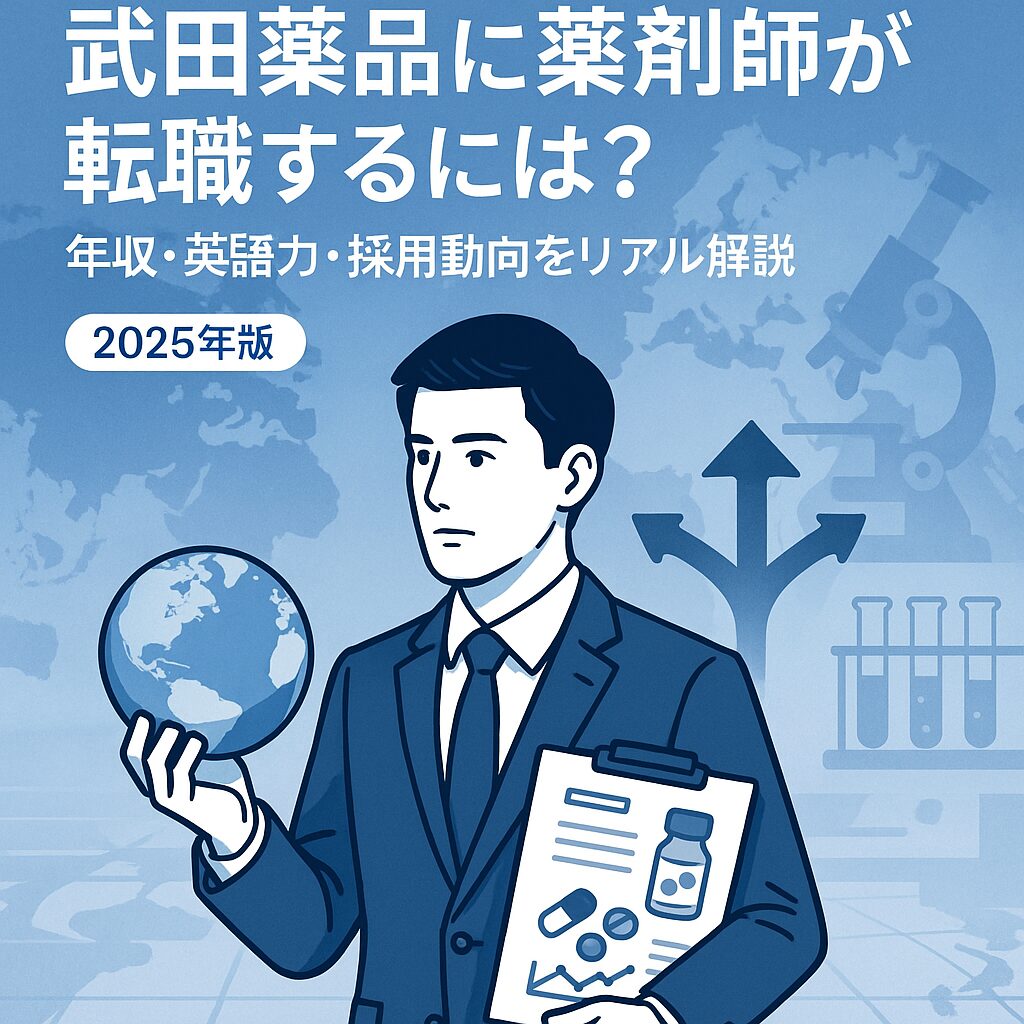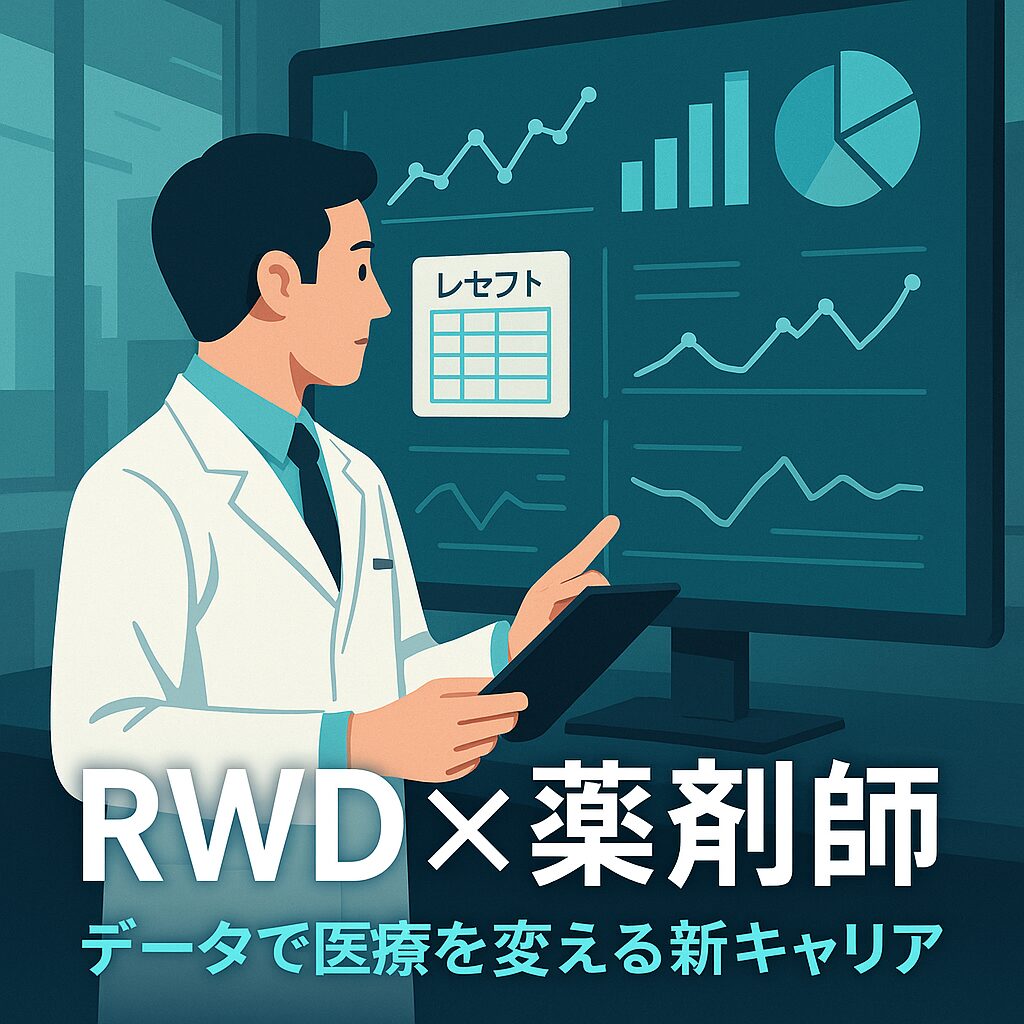“You like craft beer?” 外国人同僚のひと言から始まった、虎ノ門ヒルズで感じた外資系カルチャーのリアル

外資系企業で働くようになって驚いたのは、何気ない雑談から広がる“世界の広さ”でした。
ある日、外国人の同僚から「クラフトビール好き?」と聞かれたのがきっかけで、虎ノ門ヒルズにある「UCHU BREWING」へ。
そこには、外資系らしい自由な空気、人とのちょうどいい距離感がありました。
今回は、そんな日常のひとコマを通して見えてきた「外資系カルチャーのリアル」をお届けします。
きっかけは外国人同僚の一言から
「You like craft beer?」から始まるナチュラルな雑談
ある日の午後、仕事終わりに雑談していたときのこと。
外国人の同僚がふと、こんなふうに声をかけてきました。
“You like craft beer, right? There’s a great one in Toranomon Hills.”
(クラフトビール好きだよね?虎ノ門ヒルズにいいとこあるよ)
外資系企業で働いていると、こうした“自然体の会話”が日常的に交わされる場面がよくあります。
とくに雑談のトピックは、趣味・食べ物・最近のお気に入りなど、パーソナルな話題が多く、
気取らない距離感でのコミュニケーションが、チームの一体感を育てているのを感じます。
多国籍チームだからこそ、趣味や情報の幅も多様
この日おすすめされたのは、「UCHU BREWING(宇宙ビール)」という国産クラフトビール。
私はその名前すら知らなかったのですが、彼いわく、
“That’s one of the boldest DIPAs in Japan. It’s worth the hype.”
(日本で一番パンチあるDIPA(ダブルIPA)だよ。話題になるのも納得って感じ)
同僚の出身国はアメリカ。IPAに詳しい人が言うなら…と興味が湧いて、
その週末に虎ノ門ヒルズのUCHU BREWING直営店へ足を運ぶことにしました。
こうした“文化の違いをベースにした情報の共有”が、日々の業務外でも豊かな学びにつながっているのは、
多国籍なチームだからこその魅力です。
ちょっとした会話が“文化の違い”を楽しむきっかけに
このエピソードを通じて改めて感じたのは、“外資系の多様性”は単に国籍の違いではなく、価値観や話題の豊かさにあるということ。
- ビールひとつでも「どういう視点で評価するか」が違う
- おすすめの仕方も、日本的な遠慮ではなく「とりあえず試してみてよ」というライトさ
- その違いを楽しみながら受け止められる風土がある
こうした日常の中の「ちょっとした国際感覚」が、視野を広げたり、会話力を育てたりするんだと実感します。
「語学力より“聞く力”と“好奇心”の方が大切」だとよく言われる理由も、こういう場面から自然と腑に落ちました。
関連記事への内部リンク
- 外資系薬剤師が直面する文化ギャップ|日系との違いと乗り越え方を解説
→ 「YES/NO」よりも「なぜそう思うか」の伝え方が重視される文化とは? - 外資系に向いている薬剤師・向かない薬剤師の特徴
→ 英語力よりも“人との距離感”や“柔軟さ”が鍵になる理由を解説
虎ノ門ヒルズで出会った“宇宙ビール”と外資系の空気感
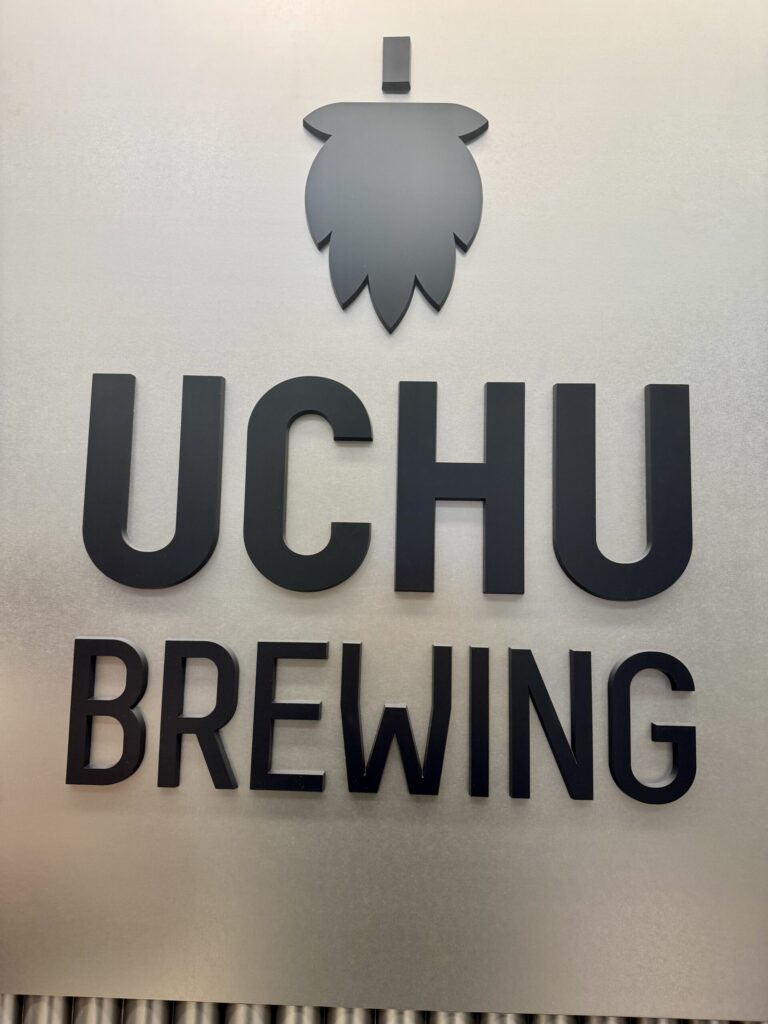
UCHU BREWINGの店舗とラインナップの紹介
虎ノ門ヒルズの地下にある「UCHU BREWING」は、国内外のビール好きをうならせる山梨発のクラフトビールブランド。
店舗のデザインはまるで実験室のようで、壁には大きくホップをかたどったロゴが掲げられていました。
この日購入したのは、同僚にすすめられた3本:
- MASTER(DDH DIPA):エジプトの神官のような犬のラベルが印象的な超濃厚ビール
- PURE HORIZON(DDH WEST COAST IPA):海のグラデーションが美しい、すっきり系
- Zenbu Burokkori(DDH DIPA):見た目も味もパンチの効いた“全部ブロッコリ”なネタ系ビール

商品ひとつひとつにストーリーがあり、どれも**会話のきっかけになる“個性”**を持っています。
この「遊び心」と「本気」が共存する感じに、どこか外資系のカルチャーと通じるものを感じました。
上司やチームにお土産話をする“オープンな空気”
週明け、軽い気持ちで「この前おすすめのビール、買ってみたんですよ」と話すと、
思いのほか上司も同僚も反応してくれて、
- 「どれ買った?俺は“MASTER”が推しだな」
- 「え、全部ブロッコリって何(笑)?」
といった軽い雑談で盛り上がりました。
驚いたのは、こうしたプライベートな話題を気兼ねなくシェアできる雰囲気が自然にあること。
日本企業で働いていた頃は、「業務と関係ない話題は控えるべき」という空気もありましたが、
ここでは「雑談=信頼関係を築くための潤滑油」として歓迎されている印象です。
しかも、こうしたカジュアルなやり取りが、日々のチームワークにもプラスに働いていると感じます。
「職場=仕事だけの場ではない」と気づかせてくれた瞬間
この一連の出来事を通じて強く感じたのは、
「外資系の職場は、仕事だけの場ではなく“人と人との関係性が自然に存在する場所”なんだということ。
- 雑談に寛容な空気
- “個”を尊重しながらも適度につながる文化
- オンオフの切り替えが柔軟
UCHU BREWINGのビールを買いに行ったという何気ないエピソードが、
結果的に**“この職場で働く意味”をもう一段深く感じさせてくれるきっかけ**になりました。
関連記事への内部リンク
- 外資系製薬企業のワークライフバランス事情
→ 育児・介護・趣味など、個人のライフスタイルと共存する働き方とは? - 企業薬剤師の仕事と役割とは?
→ 実は“対話力”や“関係構築力”が求められる企業での薬剤師業務。その実態に迫る。
【企業に興味はあるけれど、何から始めればいいか分からない方へ。】
業界・職種の全体像と転職5ステップを、実例とともにわかりやすく解説しました。まずはこちらのガイドで、あなたのキャリアの方向性を整理してみませんか?
外資系で求められるのは「英語力」より“伝え合う姿勢”
完璧な英語より、好奇心・雑談・聞く力の重要性
「外資系=英語が話せないと無理」と思われがちですが、実際に働いてみて感じるのは、
“完璧な語学力”よりも“伝える姿勢”のほうがよほど大事だということです。
たとえば、今回のようなクラフトビールの話題も、
ネイティブレベルの英語で話す必要はありません。
「オススメしてくれたビール、買いましたよ」
「どれが一番好き?」
そんな簡単なフレーズだけでも、チームとの信頼関係を築く入り口になります。
むしろ、
- 相手の話にしっかり耳を傾ける
- 話題に興味を示す
- 自分なりの感想や体験を返す
こうした**“会話を通じて関係性を育てる力”**が、外資系では高く評価されます。
【「英語が不安で転職に踏み出せない…」そんな薬剤師の方へ】
TOEICの目安、英語力が活きる職種、学び直し法までを1本にまとめた実践ガイドをご用意しました。英語を“武器”にしたい方は、ぜひ参考にしてください。
薬剤師×英語完全ガイド|TOEIC・外資転職・学習法を実例で解説
「飲みにケーション」より自然な“ゆるい交流”
日本企業にありがちな「飲みに行って本音を言う文化」は、外資系にはあまりありません。
代わりにあるのは、**“自然体で、日常の中で少しずつ距離を縮めていく”**というカルチャー。
- オフィスのバーカウンターで軽く一杯
- ランチ時にお気に入りのカフェを教え合う
- スモールトークの延長でプライベートな話題に触れる
こうした**強制されない“ゆるい交流”**こそが、信頼を築く土台になっていて、
結果的に仕事の連携やミーティングの空気感もスムーズになります。
つまり、「人と関わろうとする姿勢」が評価される環境なのです。
距離感を保ちつつ関係構築できる人材が評価される
外資系では、“フレンドリー=馴れ馴れしい”ではなく、
相手の文化やスタンスを尊重しつつ、自分のスタイルで関係性を築ける人が求められます。
たとえば、
- 雑談はするけれど、無理にプライベートに踏み込まない
- 話しかけられたら笑顔で応じ、必要があれば自分からも声をかける
- 意見が異なるときも、対立ではなく対話として向き合える
こうした**“適度な距離感を保ちながらの信頼関係づくり”**ができる人は、
外資系企業において非常に重宝されます。
つまり英語力に自信がなくても、
相手と対話する意志、文化を尊重する姿勢、関係構築への柔軟性があれば、十分に通用するのです。
関連記事への内部リンク
- 英語だけじゃない!外資系で評価される人物像
→ 語学よりも“態度と姿勢”が評価につながる理由とは? - 薬剤師が企業で活躍するために必要なスキル
→ 対話力・提案力・柔軟性。専門性だけではない“企業での活躍条件”を整理
「カルチャーが合うかどうか」が転職の成否を左右する
雰囲気の違和感は“成果”よりも“継続”に影響する
転職を成功させるために、年収や業務内容を重視するのは当然のこと。
でも、実際に企業で働いてみて強く感じたのは、
「カルチャーが自分に合うかどうか」が、働き続けられるかを決める大きな要因だということです。
たとえば——
- 周りがガツガツしていて、毎日が消耗戦のように感じる
- 雑談ひとつにも気を遣いすぎて、自然体でいられない
- “暗黙のルール”が多すぎて、行動する前に悩んでしまう
どんなに待遇が良くても、こうした“職場の空気感”が自分と合わないと、
パフォーマンス以前に気持ちが持たなくなるのです。
つまり、カルチャーとの相性は「成果」よりも「継続」に直結します。
カルチャーとの相性は情報収集と“対話”で見えてくる
とはいえ、「社風が合うかどうか」は求人票や会社HPではわかりません。
実際に働いている人の声や、“リアルな空気感”をどれだけ集められるかが鍵になります。
そのためには以下のような情報源を意識して活用しましょう:
- 現職者・元社員の口コミ(SNS、イベント、noteなど)
- 業界に詳しい転職エージェントの内部情報
- 面談・面接時の雰囲気や、社員のリアクション
特に、エージェントを活用する際は「スキルマッチ」だけでなく、
**“どんなチームか?” “どんな上司か?” “会話の温度感は?”**といった点にも注目して、
“対話ベースの情報収集”を意識するとミスマッチを防ぎやすくなります。
エージェントに「雰囲気」や「チームの空気感」を相談してみよう
転職エージェントというと、求人紹介や書類添削がメインだと思われがちですが、
実は**「企業カルチャーとの相性」まで見てくれるかどうかが、信頼できるエージェントの見分け方**でもあります。
たとえば以下のような質問をしてみましょう:
- この企業はフラットな雰囲気ですか?上下関係は強いですか?
- 雑談が多い/少ないチームですか?
- 過去に入社した人の定着率や、辞めた理由は?
これらの質問に明確な回答をくれるエージェントであれば、
“スキル”と“カルチャー”の両方に配慮した転職支援ができるパートナーです。
薬剤師の外資系企業転職に強い転職エージェント5選【英語×キャリアアップ】
『カルチャーマップ』紹介
外資系企業に転職を考える上で、「その会社のカルチャーと自分が合うかどうか」は、条件以上に重視すべき判断軸です。
とはいえ、“カルチャーの違い”というものは、目に見えづらく、感じ方も人それぞれ。
そんなときに参考になるのが、**エリン・メイヤー氏の著書『カルチャーマップ』**です。
⸻
『カルチャーマップ』とは?
この本では、世界各国のビジネス文化を8つの軸でマッピングし、
「どう違うのか」「どうすれ違うのか」「どう理解し合えばいいのか」を具体的に解説しています。
代表的なカルチャー軸 日本 vs 欧米の違いの例
コミュニケーション 高コンテクスト(日本) vs 低コンテクスト(米・独)
ネガティブなフィードバック 間接的(日本) vs 率直(オランダ・ドイツ)
決定の進め方 合意重視(日本) vs トップダウン(米)
この違いを知らずに働くと、
「なぜか評価されない」「報告したのに伝わってない」といったカルチャーギャップによる摩擦が起きやすくなります。
外資系を目指す薬剤師にとっての学び
実際に外資系企業で働いてみて痛感するのは、“正しい伝え方”や“納得のさせ方”は、文化圏ごとに全く違うということ。
この本は、「自分の伝え方・受け取り方が世界基準でどう見えるのか」を知る上で非常に参考になります。
とくに薬剤師のように、専門知識や論理性を求められる職種で、国際的な環境で働く人には、
「どのように説明すれば通じるか」「どんなフィードバックが望ましいか」などのヒントが詰まっています。
外資系のカルチャーを「ただの印象」や「経験則」で捉えるのではなく、構造的に理解する手段として、
この『カルチャーマップ』は、まさに“転職前の教科書”といえる一冊です。
【▶︎ 書籍リンク】
『カルチャーマップ 世界のビジネスに通用する「文化の読み方」』|エリン・メイヤー著
『カルチャーマップ』を読んで外資系で評価される薬剤師に|文化の違いを“武器”に変える1冊
関連記事への内部リンク
- 薬剤師向け転職エージェントおすすめランキング
→ “企業カルチャーの情報収集力”にも注目したエージェントを厳選紹介 - 初めての外資系転職で失敗しないポイントとは?
→ 給与や職務内容だけで選ばない。ミスマッチを防ぐ判断軸を解説
“空気が合うかどうか”が、長く働けるかを決める
今回のような、たった一本のクラフトビールをめぐる会話や出来事の中に、
外資系企業で働くことの“本質”がぎゅっと詰まっていた気がします。
- 上下関係よりもフラットな関係性
- 雑談の中に信頼がにじむチーム文化
- 無理をしなくても、自然体で関係性を築ける距離感
こうした“職場の空気感”は、実際に働いてみないとわからない部分でもあります。
けれど、英語力や専門性以上に、チームに馴染めるかどうかは、
転職の成否——もっと言えば、「その職場で心地よく続けられるかどうか」を左右する大切な軸です。
「なんとなく今の職場に違和感がある」
「条件は良いけど、人間関係にストレスがある」
そう感じているなら、次は“カルチャーが合うかどうか”を基準に転職を考えてみてもいいかもしれません。
まずは、企業の空気感やチームの雰囲気まで熟知している転職エージェントに相談するところから始めてみましょう。
情報だけでなく、“働く自分の姿”がリアルにイメージできるようになるはずです。
【「どのエージェントが自分に合うのか分からない」そんな悩みを持つ薬剤師の方へ】
22社を“16項目でスコア化”した比較表から、目的別に最適な3社がすぐに見つかります。迷っている方こそ、一度チェックしてみてください。
薬剤師転職エージェント22社比較|16項目で目的別に最適3社が見える
【「やっぱり気になる薬剤師の年収。」】
年収が上がりにくい理由と、転職・昇進・副業という“年収アップの三本柱”を、薬剤師×FPの視点でやさしく解説。将来に向けて収入を見直したい方は、ぜひ参考にしてください。
【キャリアを広げたい薬剤師のために、代表的な5つのキャリアアップルートを実例つきで解説】
必要なスキルや年収に加え、FP視点で見た「投資効率の良い成長戦略」も紹介しています。将来の選択肢を整理したい方は、まずこちらをチェックしてください。
薬剤師キャリアアップ完全ガイド|5ルート・実例・投資効率まで網羅
【「老後や住宅ローン、子どもの教育費…薬剤師のライフプラン、これで大丈夫?」】
そんな不安に向き合い、年収・家計・貯金目安までをわかりやすく解説。FP視点で“転職後の暮らし”まで考えたい方におすすめです。
薬剤師のライフプラン完全ガイド|家計・貯金・将来設計をFP視点で整理